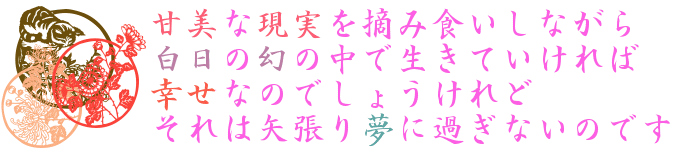|
黒猫、虎、獅子、つまりネコ科。雲雀さんに対するわたしが持つ印象はと云えば、獰猛さと鋭さを持ち合わせて、人に懐かない動物だった。顔は好いのに性格は、何て言葉を聞く度に、わたしは違和感を感じる。あの人は気高いから綺麗なんだとわたしは勝手に解釈しているからだ。今更にこやかに応対なんてされた日には卒倒する。世界が打ち壊されたかと思うだろう。我儘で自分勝手で自分の思い通りの世界を構築する人間、それが許される程の力を持った人間、それこそが雲雀恭弥なのではあるまいか。そんな話を草壁先輩とした憶えがある。 応接室の扉を開けると、風紀委員長専用と化した机と椅子の向こう側の窓から外を見下ろす雲雀さんがいた。風で柔らかな黒髪が揺れている。一瞬、此処は俗世間と乖離した場所なのではないか、なんて錯覚した。しかし瞬きをすれば、此処は見慣れた応接室に戻り、雲雀さんの肩に掛けただけの学ランの袖がはためくのが視界に入る。そして彼は、わたしを見た。黒曜石みたいな真っ黒の目だ。 「何の用?」 「先輩、式だけ出たら、直ぐいなくなっちゃったじゃないですか。写真を撮りたくて」 「どうして僕がそんなことしなきゃいけないの」 「わたしが雲雀さんと写真を撮りたいからです」 「嫌だね。君と群れた証拠なんて残したくない」 「群れるんじゃありません」 「それじゃあ何?」 「擦れ違ったのです。ほんの少しだけ、時間を共有したって記録です」 「ふうん、」 わたしの手に収まったポラロイドカメラを静かに見詰めた後、彼は手招きした。相変わらずの仏頂面だ。わたしは頭に浮かんだ福ではなく厄介事を呼びそうな招き猫を直ぐに振り払い、出来るだけ静かに、雲雀さんに近付く。此処で無駄な音を立てたら、きっとこの空間の非現実味は崩れてしまう。 「ねえ、なんでそのカメラなんだい?」 「情緒があると思いませんか?」 「草壁とはデジカメで撮ったって聞いたけど」 「雲雀さん以外はデジカメです」 「へえ」 「草壁先輩、来たんですか」 「追い出した」 「わたしも邪魔ですかね」 「まあ、君なら少しなら居ても良いよ」 ポラロイドカメラ。玩具のような見た目のそれは、やはりデジタルの最先端技術に比べれば写りが良い訳ではない。だから良いのだ。余分なものが写らない。写真は目に見えるもの全てを写し出そうとしてしまう。それらの幾らかを欠損させたなら、目には見えないものをも写し出してくれるかもしれない。そしてこれは、その場で写真を排出する。空間や時間を歪曲させて切り取って、平面に描き出す。匣の中に記憶を留めはしない。直ぐに忘れてくれる。そう云えば、写真機が登場した当初は、被写体は魂を吸われるだとか云う風聞が囁かれたそうだが、わたしは強ち間違いでも無いと考えている。写真家が撮った写真でも素人のものでも、吸い寄せられるような魅力に満ちたものがある。無意識の内に、其等に籠められたエネルギイだとか、非科学的な力を受信しているのではないだろうか。一時的に機械が吸い取った魂が目には見えない形で写し出しているのだと思う。そんな話を雲雀さんとしたような気がする。多分、ポラロイドカメラのデータと同じように覚えてはいないだろうけれども。 物凄く広い部屋と云う訳でもないのに、雲雀さんの隣に行くのに時間が掛かったように思える。まるで、此処だけ時間の流れがゆっくりになっているようだ。それはわたしの願望なのかもしれない。時間よ止まれ!彼を連れて行くな!しかしながら、それではわたしはただの駄々っ子になってしまう。ぽつねんと時間に取り残されてみたいが、ピーターパン症候群でもあるまいし、と褪めた結論に毎度ながら辿り着いてしまうのだった。 「君が撮るの?」 「はい、」 いきますよ、とカメラを握って腕を伸ばす。レンズは少し上から雲雀さんとわたしを見下ろしている。少しだけ口の両端を上げて、シャッターを押す。魔法に掛かる音がした、カシャッ。わたしたちが此処で並んだ痕跡が吐き出される。未だ発色が不完全なそれを二人で覗き込む。頬骨の上がった大して美人でも可愛くもないわたしと、つんと澄ました誰より綺麗な彼。わたしたちの関係性そのものじゃあないか。 「上手いじゃないか」 「ありがとうございます」 「頂戴」 「ああ、はい、どうぞ」 半ば引ったくるようにわたしから写真を取り上げ、何も置かれていない机に放った。あれだけプリントが積まれていたのに、気付けば空っぽだ。此処に先輩たちがいなくなって、いたことさえなくなってしまうようで、突如として酷く寂しくなった。 「僕が撮る」 「え、」 「貸しなよ」 呆けていたわたしの手からポラロイドカメラを奪って、不思議そうにそれを眺める。黒くて形も無骨だが、わたしはカメラ自体に可愛さを求めてはいないし、尤も、これには機能も求めていない。 「此処を押せば良いの?」 わたしが頷くと、雲雀さんはレンズを此方に向けたまま腕を伸ばす。そして、もう一本の腕がわたしの肩に回った。ぐい、と引き寄せられ、体が横に傾く。彼は一見すると華奢でたおやかだが、実際は運動部顔負けの運動能力を持ち合わせている。トンファーを振り回して、自分より一回りも二回りも大柄な相手を薙ぎ倒しているのだから、当然と云えば当然なのだけれど。わたしはと云うと、彼の腕が触れた二の腕の贅肉が気になる年頃で、風紀委員の癖に運動神経皆無で、逆に風紀委員であるせいで逃げ足だけは自信を持てるという一般的な中学二年生、序でにちょっと中二病気味。雲雀さん曰く、「君はそのままで良いよ、ガタイが良い君を想像したら笑えたから」。寧ろ余分なお肉を落としたい。 「近くないですか」 「遠くはないね」 背中から他人、つまり彼の体温を感じる。今まで、他人所か親にさえ抱き締められた記憶がないわたしとしては、ぽかんとする他ない。いや、抱き締められたことはあるのかもしれないが、幼い頃の記憶というのはどうでも良いことを除いて疾うに失せてしまっているように思える。それにしても、あの雲雀さんだ。わたしが思うに学校一の美人で一匹狼の雲雀さんにこうして接近されているのだ。心臓の音はフォルティッシッシモだ。スフォルツアンドだ。 「撮るよ」 笑顔なぞ作れる筈もない。カシャッ。間。目を大きく開いたわたし顔の斜め上に意地の悪い笑みを浮かべた雲雀さんが写った写真が手渡された。いつにも増して不細工な顔になってしまったが、それを口にすると、「何処がだい?」と本心が何処にあるのかよく分からない言葉を返されてしまった。 「僕はね、これでも君のことを結構気に入っているんだよ」 「はあ、」 「じゃなきゃ、次の委員長になんてしない」 そうなのである。わたしは泣く子も黙る並盛中風紀委員長という役職を引き継がされてしまったのである。それも、「次の委員長は君だから。断ったら咬み殺す」の二言で。わたしは雲雀さんと違って喧嘩は口喧嘩しかしたことがないし、カリスマ性も全くない。暴力政治で不良集団を纏めることも出来ない。にも拘わらず、草壁先輩は「今日から委員長か姐御と呼べ」なんて暴走族の引退挨拶かというようなノリの集会で言ったものだから、わたしの学級の沢田と獄寺の如き関係が一瞬にして出来てしまったのだ。まるで極妻だ。スケ番だ。 「わたしは雲雀さんのように並盛の風紀を守ることは出来ません」 「知ってるよそんなこと。並盛は僕が守るんだから」 「じゃあ、どうしてわたしを、」 「気に入ってるからだって言ったの、聞いてなかったのかい?」 「聞いてました」 「君が戦うことなんて微塵も期待していない。そんなのは君のクラスメイトにやらせれば良い」 「確かに」 「僕はね、自分のものを誰かに譲るのが大嫌いなんだ」 「でしょうね」 「並盛中風紀委員長は僕のものだ。だけど、君になら預けても良いと思ってる」 そんな傲慢なことを云っても赦されるのは、わたしが知る限り、彼くらいのものではないだろうか。例えば草壁先輩にそう云われたとして、風紀委員長と云う重責を引き受けることに納得するとは思えない。わたしは本当に、彼の気紛れではなく、本当に気に入られていると、自惚れても良いのだろうか。 「君は寝坊ばっかりでいつも遅刻ぎりぎりで、その癖校門を時間内に通って行くし、口は達者なのに運動音痴だし、書類間違えて文書は大抵誤字脱字があるし、紅茶も珈琲も溢す上にカップも割った」 「…相違御座いません」 「でももう、誰にも文句は云わせない。風紀委員長の立場は絶対なんだから」 「雲雀さんや草壁先輩にはいつまでも怒られそうですが」 「その代わり、君は草食動物であることをやめなければならない」 いつもより更に鋭さを増した双眸と吊り上げられた唇に、わたしはただ黙るしかなくなってしまった。しかしながら、他人を蹴落として生きていく草食動物、それも雲雀さんが望んでいるのはヒエラルキイの頂点じゃないだろうか、になれ、と云われてもなれる筈もない。やってみなくても分かる。寧ろなりたくない。 「雑食になります」 「君に雑食なんて器用な真似は無理だよ」 「肉食の方が無理です」 「無理だ」 「じゃあどうしろって云うんですか」 「簡単さ。人間になれば良い」 にやり、と。音を当て嵌められるような笑い方をする雲雀さんはチェシャ猫のようで、言っている言葉も曖昧で謎かけのようだ。わたしはアリスみたいに可愛くはないのに。 「その憎たらしい口先で草食動物共を蹂躙すれば良いじゃないか」 「随分簡単に云いますね」 「他人事だからね」 確かにその通り、他人事だ。「だって君は、自分以外は他人だって割りきってるでしょ」、と付け加えられる。そんな風に思われていたとは心外だが、強ち間違ってもいないように感じた。 「雲雀さんのことなんて、考えたって分からないと思ってるだけですよ」 「僕だって、君の考えてることが分からない」 「そんなものですよ」 「うん、そんなものだ」 草食動物の世界で人間になると云うことはつまり、弱肉強食の世界とは別次元に一人で生きてゆかねばならないのだろう。無謀だ。わたしには、可愛い子振るつもりは微塵もないが、一人で生きていけるような力はない。一人で何でも出来る、なんて気取って見せた所で、虚しさに押しつぶされて終うだけだろう。そこで、ふと思い出す。雲雀さんはわたしが他人と線引きしていることを感じ取っているのだ。人間と動物は歩み寄ることは出来ても、結局は別の生き物だ。多分、そう云うことなのだろう。そんなものかあ、と再度口にすると、軽く頭を叩くように撫でられた。今日は初めてされたことばっかりだ。いつもはこんな生意気なことばかり云っていたら咬み殺されそうになるのに。雲雀さんがいつもの雲雀さんじゃないようで、また寂しくなった。それとも、これが本当の雲雀さんで、昨日までのわたしが見ていたのは幻だったのだろうか。いいや、きっとあれは全て同じ現実だ。あんな暴君が二人といて堪るものか。 「困ったことがあったらいつでも呼びなよ。僕が助けてあげる」 「雲雀さん直々に、ですか?」 「そうだよ。君を選んだ責任は最後まで果たすさ」 そして、雲雀さんは写真を手に、応接室から、この学校からも去って行った。わたしは泣くことさえなかったけれども、何も考えられず、ぼんやりと窓から校庭を眺めていた。人が蟻のようだ。窓枠に肘を付いて、頬杖を付く。目を閉じる。夕方まで、この部屋で過ごすつもりだ。今日はこれ以上、卒業生に会いたくないからだ。雲雀さんを最後にしたかったのだ。 雲雀さんは獣だ。人間には飼い慣らされたりしない、気高い獣だ。だから誰にも彼の気持ちを理解して貰えないし、誰にも近付かないし、近付けない。我が儘で自分勝手で集団生活には不向き。けれども、わたしは彼を自分の同類だとは思ったりしない。たった今から、わたしは飼い慣らす側の人間になることを決定付けられてしまったのだ。わたしを守ってくれると云うのが彼の責任ならば、これがわたしの責任だ。雲雀さんは、素晴らしい先輩だ。単なる気難しい先輩だと思っていた過去の自分をひっぱたいてやりたい。しかしながら、下世話な同級生に雲雀さんが好きなのかと訊かれれば、尊敬しているとしか答えないだろう。恋することなんてないだろう。好きは好きでも憧れと恋は違う。単にわたしは、あなたがすきだったのです。きっと明日から、あなたがいないこの部屋が広く感じるのです。けれどきっと、直ぐになれてしまうのだろうと思います。わたしはあなたがだいすきなのです。 「さよなら」
(090329/090425加筆修正/フリー配布期間は終了しました) |